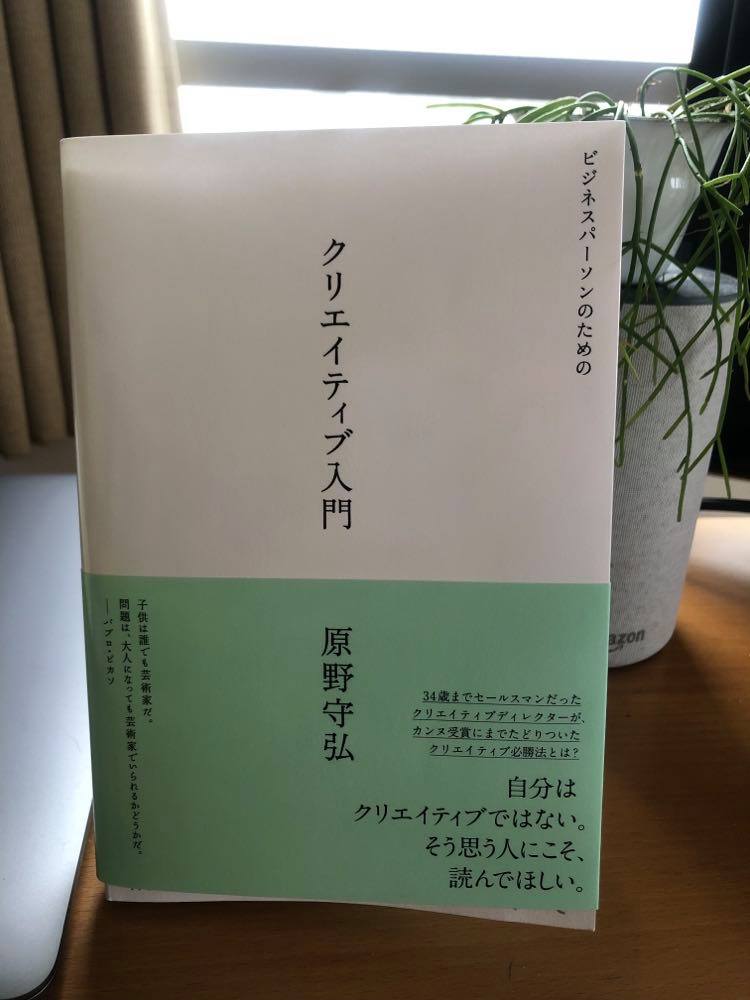僕の中には、決して自分で手懐づけることのできない、もう一人の自分がいる。頭では合理的に考えつつも、結局はいつも非合理な感情を優先してしまう、厄介な「自分」だ。
ちょっとした買い物から、車とかの大きな買い物の決断まで、結局自分を動かすのは感情のほう。
世間一般の人と相対的に比べれば、かなり自分は理性が優先するほうだと思う。けれど、そんな自分でも結局は感情でしか動かないことに対し、なんで?って自分でも思っていた。
この原野さんの本で、一発でその謎が解けた。
人が感情で動くのは、脳の作りの問題であると。
論理をつかさどる「大脳新皮質」は、優れたCPU。
言語や数値などを論理的に処理することが出来るが、肝心の意思決定が出来ない。
意思決定を行うのは、脳の真ん中にある「大脳辺縁系」。
ただし、この脳は言葉や論理を理解することが出来ない。
意識下の自分=大脳新皮質では司ることのできない、言葉が通じない大脳辺縁系こそ、もう一人の自分の正体だ。
そうか、脳の作りなのか。それならば仕方ない。。。
この脳の作りは、クリエイテイブの世界、あるいは人を動かす、ということにおいて前提となる。
数値や理屈をどれだけ並べても納得してもらえなかったり、あるいはビジネスの場面で決裁を得られないのは、結局は大脳新皮質にしか届いていないから。
大脳辺縁系に直接コミュニケーションをとらねばならない。
そのためには、WhatやHowよりも、Whyが大事。
僕たちの心に刺さるブランドはすべてWhyを語っている。
—
その他にも、この本には素敵な言葉がたくさん散りばめられている。
すべては「個人的な好き」から始まる
感情でしか人を動かせないわけだから、人を動かすことのできる感情、つまり「好き」を大切にしよう。
まずは、個人的な「好き」という感情を大切にして、それを集め、「好き」に対するアンテナを磨いていく。市場性の高い「好き」ならば、多くの人に共感を得ることが出来る。
優れたブランドは自分を語らない。自分が愛するものについて語る。
脳の話に繋がるが、自分の優れた点を語ったところで、大脳辺縁系には届かない。
それを分かっているブランドは、自分の「好き」なものについて語り、人々の脳の奥に届き、そして共感され、愛される。
巨人の肩の上に立つ
~私がかなたを見渡せたとしたら、それは巨人の肩の上に立っていたからです~」(アイザック・ニュートン)
ゼロからアイデアが生まれることはほとんど無く、過去の優れたものに刺激を得たり、優れたもの同士をくっつけたり、その繰り返しだ。
その循環を原野さんは、
「好きになる。好きを盗む。好きを返す」と表現されていた。素敵だ。
ただ真似るだけでなく、「盗み」、そして自分の好きを混ぜ合わせて新しいものを創造していく。そして、それをまた巨人に還元していく。
自分の好きを集め、言語化し、抽象化し、新たなアイデアを生み出していく。そんなクリエイティブな作業の先にある、たどり着きたい場所は、皮肉にも言語が通じない脳味噌なのだ。
とても深い。